
第1話 オフィス「風の予感」 =6=
|
掃除を切り上げた僕たちは、アングルを変えて十数枚の写真を撮った。 それから、暗幕を撤収する。その間に、杉橋はトラックを再び表にまわしてきた。プレートも「電気工事」のものに張りなおしてある。 「窓が暗幕で閉ざされた写真だけでは、無理ですから」と、杉橋は、暗幕を外したあとに、もう一度カメラを構えた。 「じゃあ、さっき撮った写真は?」 「ストロボがガラスに反射して、ありえない位置に不自然な光を映すかもしれません。だから、暗幕を使った写真も必要なんです。それらをあとで合成することになります。ここでは仕上がりを確認している暇はありませんから、ホテルに戻ってからの作業ですね」 暗幕を取り去ってのストロボ撮影。 当然のことながら、外に光が漏れる。 誰かに目撃されればあきらかに不自然な事態である。 なにしろ、閉店したはずの、しかも無人のお好み焼き屋の窓や玄関ガラスから、時折閃光が放たれるのだ。 「時間との勝負ね」と、清花が身構える。 「どんなに早く済ませても、運に左右されます」と、杉橋も緊張気味だ。 道具類のトラックへの積み込みは終えている。 僕たちはそれぞれデジタルカメラを持ち、役割分担されたアングルで写真を素早く撮り終える。そして、トラックに逃げ込んでさっさと出発。これがシナリオだ。 「じゃあ、さくっと撮って、ダッシュで逃げましょう」 清花が宣言したその時だった。 気配を感じた。 隣の文房具屋だ。 3人が3人とも、同じ方角を向いたのだから、僕の気のせいではない。 僕はカメラを持った手を構えかけていたが、ビクリとして、手を引いてしまった。そのとき、肘が壁に当たった。小さな音だが、それがとてつもなく大きく響く。他に音源が何も無いから、無音状態に解き放たれた唯一の物音だ。 「まずいわね」と、清花。 「まずいですね」と、鸚鵡返しする杉橋。 文房具屋方向からアクビの声がする。聞き覚えがある。間違いない。隣の主人だ。 「夜中の散歩って、いつものこと?」 清花が僕に問うが、そんなこと知るわけが無い。 そう答えると、「そうよね」と言う。「いつものことなら心配ないわ。でも、いつもと違う何かを感じて、目を覚まし、外に出たんなら、まずいわね。そういうときの人間の神経って、敏感だから」 「いつものことなら、なお心配ですよ」と、杉橋。「表の軽トラ。あんなにはっきりといつもと違うものがあったら、普通は警戒します」 「じゃあ、どうするのさ」と、僕。 「待つしかないわ。まさか夜が明けるまで、ずっとそこにいるなんて考えられないもの」 清花の提案が、ベストかどうかはわからない。その間に、近所の誰かに気付かれたらアウトである。 「僕が、なんとかするよ」 物音を出してしまった責任を感じたわけではない。試してみたい方法があった。 「なんとかって、どうするの?」 「2階へ上がって、窓から電柱に飛び移る。で、電柱から降りてくる。車には電気の点検業者のプレートが貼ってあるし、僕たちは作業服を着てるから、それで納得してくれると思う」 「そうね。パッと見、不審な車であっても、納得したら、ふ〜んって家に戻ってくれるかもしれないわね」 「そうですね。表に軽トラも置きっぱなしですし、何だこの車とか思われて、警察を呼ばれたりしてもコトですしね」 僕のアイディアに清花も杉橋も賛成してくれた。 「でも、電柱には、わたしが登るわ」 「いや、清花にそんなこと、させられないよ」 「和宣はダメ。お隣さんと、面識があるわ」 「あ!」 そうだった。僕は昨日、お好み焼き屋について、根掘り葉掘り聞いたばかりである。そんな男が「電気の点検です」なんて言っても、信用してもらえまい。おまけに僕は名刺を渡している。 「いい、じゃあ、こういう作戦でいくから」 |
|
危機に立たされたときにこそ、本当のチームワークが試される。 僕は心の底から、そう思った。 2階の窓から電柱に乗り移った清花は、打ち合わせどおり、スパナを落とした。 高位置から地面に叩きつけられたスパナは、アスファルトとアルミのぶつかる音を何度か繰り返しながら、軽トラックの陰までバウンドとスライドで転がってゆく。その後、清花は電柱を降りてスパナを探し、こんな真夜中だけれども確かに工事中なのだと文房具屋に思わせる、という手はずである。 僕と杉橋はお好み焼き屋の中で身を潜めている。だから、清花の行動を見ることはできない。けれど、彼女が電柱から降りてきた気配を感じない。 あとで訊くと、ベルトがなにかにひっかかって降りられなかったとのことだが、この時の僕たちに知る由もない。 「おかしい。なにかあったようです」 杉橋の判断は早かった。 お好み焼き屋を音も無く飛び出してゆく。 そして、さも今、電柱から降りたかのように装って、「あれ? どこ、行った?」と、スパナを探すフリをした。 タイミング的には微妙なのだが、杉橋は一方的に文房具屋の主人に話しかけて、考える余地を与えない。 「こんばんわ。夜分にお騒がせして申し訳ありません。停電の苦情がありまして、この付近を順次検査しています」 「停電〜? 知らんなあ〜。まあ、ご苦労さん」 予想通り、とりあえず納得した文房具屋は、家に戻った。 杉橋が、作業服の尻をぽんぽんと叩く。 合図だ。 僕はストロボを炊いて写真を撮る。清花も杉橋も抜けているので、僕が3人分を受け持って撮りまくる。ひっかかったベルトをなんとかして、清花も電柱から2階の窓へ、そして1階の店舗へと戻ってきた。 作業を終えた僕は、トラックの荷台へ。清花は運転席へ。速攻で逃げるのだから、物音がどうこうなどと言ってる場合じゃない。普通にエンジンをかけて、ふかす。助手席のドアを開け放つと、もう軽トラックは動き始める。 そこへ、お好み焼き屋を施錠した杉橋が飛び乗った。 作業のための軽トラックが来ていることを文房具屋は知っているから、再び顔を出すことは無いだろう。しかし、他の住人が物音を聞きつけて出てくるかもしれない。 だが、全ての作業は終えている。 あとは一目散に現場離脱。多分、誰にも目撃されなかっただろう。 角を曲がったところで、運転手交代。実は清花は車の免許を持っていない。 「これくらいの運転なら大丈夫だけど、でも、わたしはわたしでしなくちゃいけないことがあるからね。念には念を入れなくちゃ」 そう、念には念をだ。 僕にも忘れてはならない最後の作業がある。僕はマグネットで貼り付けられた「電気工事業者のプレート」を荷台から手を伸ばして剥がした。 |
|
杉橋が軽トラックで持ち込んだものに、ノートパソコンとプリンター、そしてスキャナがある。真夜中のホテルの駐車場にこっそりと軽トラックを止めた僕たちは、酔っ払いを装って声高にフロントを呼び出し、それぞれのルームキーをもらってから、杉橋の部屋に集まった。 遅い時間にビジネスホテルに戻り、不信感を抱かせないためには、「仕事が長引いてヘトヘト」であるか、「酔っ払っていい気分」のどちらかが適切だという清花の主張に従ったわけだが、清花だけはフリではなく、いつの間に飲んだのか、酒臭い口臭を撒き散らしていた。 「だって、1人ぐらい、本当にお酒を飲んでないと、匂いでばれるわよ」 清花の「わたしはわたしですることがある」が、酒を浴びることだったとは。確かにこれでは、運転と平行して行うことはできない。それにしても、お好み焼き屋からホテルまでは、たいした距離じゃないというのに、あのわずかな時間にどんな勢いで飲んだのだろう? 匂いは昨日以上だし、顔だって赤くなってるし、相当の量を浴びたと思われる。 にもかかわらず、作業が始まると、清花は嘘みたいにシャンとしていた。 デジタルカメラをパソコンに接続し、お好み焼き屋で取った画像を取り込む。スキャナでおばあちゃんの写真も取り込む。割烹着を着ているのが好都合だ。 ここからが画像処理ソフトの出番である。 おばあちゃんの写真から背景などを切り取って、人物だけにする。お好み焼き屋の店内の写真を修整する。例えば、鉄板の錆などは、錆びていない部分の色を拾って、その色で錆びた部分を塗ってしまうのである。 次にふたつの写真を合成する。 ここが腕の見せ所なのだそうだ。なにしろコンピューターで画像処理をするわけだから、おばあちゃんを机の上に立たせることもできるし、首から上だけを鉄板の上に載せることもできる。もちろんそんなことはしないけれど、何でもできるということはおばあちゃんをどのように配置するかに気を配らないと、不自然な画像になってしまうということだ。 「これ、宙に浮いてるように見えるよ」と、清花。 「暖簾の前に立たせたつもりなんですけど」と、杉橋。 「おばあちゃんをアップにして、足もとをうつさないようにしたらどう?」と、僕。 「やってみましょう」 さらに、暗幕で閉ざされた窓の部分に、逃げる直前に撮った写真の窓の部分を貼り付ける。 「微妙にアングルが違うな。うまくはまらない」 杉橋が悲鳴をあげた。そりゃあそうだ。三脚を設置して定点撮影をしたわけじゃない。 それに、僕たちが持っているデジタルカメラは、3台ともメーカーも画素数も違う。 「どうしましょう?」と、杉橋。 「じゃあ、もう一度忍び込んで、取り直してくる?」 清花の提案に、杉橋は「とんでもない」と首を振った。 「冗談よ」 「やめてくださいよ、たちの悪い冗談は」 明度を落とし、画素数も少なくして、なんとかつなぎ目をごまかすことができた。 「いい? この写真は複製よ。持ち主が貸してはくれたけれど、貰うことはできなかった。だから、その場で紙焼き写真をデジカメで撮って、それをプリントアウトしたものなの。だから、若干ピントが甘い。そういうことにしておきましょう」 パソコンの画面を見ながら、清花はマウスを操作する。 画質がみるみる劣化していく。 ああでもない、こうでもないと、パソコンをいじること約3時間。夜明け間近のホテルの一室で、その写真は出来上がった。 おばあちゃんは店の真ん中に立ち、左右にテーブルがあるという単純なアングル。 出来上がったいくつかの候補作品の中から、「これがベストかな」と僕と杉橋の意見があったとき、清花は座ったまま寝息を立てていた。 昨日は夜遅くまで僕とディスカッションをしていたし、今日は朝早くから自分の案件をこなすために出かけている。おそらくほとんど寝ていないはずだ。 さらに夜の10時からは僕に合流、そのまま最終電車を待って、お好み焼き屋で深夜の作業。 ホテルに戻って写真の加工。 おっと、その間に酒を大量に摂取している。これではさすがに眠ってしまっても無理はないと思う。 「さて、写真はできたけど、清花をどうしよう」 「二人で部屋まで運んで、ベッドの上にでも放り出しておきましょう」 笑う杉橋に、僕はうんうんと頷いた。 |
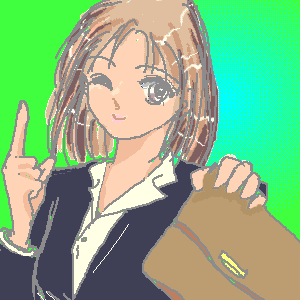 「報告書は依頼者に提出する前に社長のチェックを受けることになってるの。わたしの方の案件は今日はもういいから、今から二人でオフィスに行かない?」
「報告書は依頼者に提出する前に社長のチェックを受けることになってるの。わたしの方の案件は今日はもういいから、今から二人でオフィスに行かない?」ホテルの喫茶室でブランチを取りながら、清花が提案した。 僕に異存はない。 責任者のチェックを受けるのは当然だし、社長なる人物に逢ってもみたかった。 今朝は2人とも朝寝坊をしている。チェックアウトギリギリの時間に目覚めて、清花に電話を入れると、彼女はまだ眠っていた。杉橋は、朝早くにチェックアウトすると昨日から聞かされていた。 フロントに内線電話を入れ、僕たちはチェックアウトの延長を依頼。 一時間いくらですが、どうしますかと問われて、とりあえずシャワーを浴びて荷物を整えるだけだから、「1時間だけ」と返事した。 身の回りを整えて、1時間後に清花とロビーで待ち合わせ。そして喫茶室へ向かったというわけだ。 身体も脳もまだ眠りの余韻が残っている。だが、窓の外はしっかり真昼間だ。 室内はエアコンが効いているけれど、風景の明るさや輝き具合から、今日は暑くなりそうだと感じた。春の終りはいつのまにか初夏へと変貌を遂げている。 「ここのホットコーヒー、おいしいね」と、清花が笑う。 「そうだね」と、僕。 「でも、きっとこれは、ず〜っとエアコンの効いた室内に居たから、暖かい飲み物が嬉しいんだよね」 今度は何も返事せず、僕は頷くだけだった。 「きっと、外から戻ってきたら、アイスコーヒーが欲しくなるんだよね」 「いったい、何が言いたいの?」と、訊きかけて、やめた。 どうでもいい内容の会話だけれど、ふと感じた想いを伝え合うのは大切である。 僕に欠けているもののひとつが、これなのだ。だから、今回の案件で、「肝心な何か」を感じることができなかったのである。 「そうだよ。暑い外から戻ってきたときは、アイスコーヒーが欲しくなるもんだよ」と、僕は言った。 |
|
僕は清花に連れられるままに、電車に乗り、降り、そして歩き、一軒のマンションについた。ごく普通のワンルームマンションだ。 「ここよ」 4階の一室。「有田」という表札を清花は指さした。 ワンルームマンションをオフィス代わりに使うというのは珍しくないのかも知れないけれど、社名は出ていない。 「有田」という名には聞き覚えがある。清花が自分の過去を語ってくれたときに出てきた、「風の予感」の社長の名前だ。中にいたのは僕たちより少し年上、多分五つも差がないだろうと思われる男だった。中肉中背、無味無臭。さすがに無色透明ではないけれど、スーツを着せたら似合いそうだ。 でも彼はジャージ姿だった。 「やあどうも。僕が有田です」 僕はペコリとお辞儀をし、清花は右手を軽く上げて微笑んだ。 「あの、ひょっとして、今日はお休みですか? もしかして、ご自宅に押し掛けてしまってるのでしょうか?」と、僕は恐縮して言った。 「へ? いや、休みじゃありませんよ。この仕事に定休日はありません。仕事が切れたら休みです。あ……この格好のせいですね。どうも、すいません」と、相手も恐縮した。 「ちゃんと説明してなくてごめんなさい」と、清花が割り込んでくる。「ここは、社長の自宅なんだけど、まあオフィスみたいなもんでもあるのよ」 「オフィスみたいなもんって、そうは言っても……」 どう見てもオフィスじゃない。自宅である。だって、部屋にはベッドが置いてあるし、シンクの横には湯沸しポットがあり、小さな炊飯器からは湯気が立ち昇っていた。 「というか、オフィスなんて無いんですよ。アハハ」と、有田は言った。 「ないって、でも、一応有限会社でしょう? まあ、別に自宅でも登記はできるんでしょうけれど」 「有限会社? 清花ちゃん、そんなこと言ったの? うちは会社組織でも何でもないよ。知ってるでしょ?」 「わたし、そんなこと、一言も言ってませんけど……」 「だって、名刺にカッコ有って、書いてある……から」 僕はゴニョゴニョと口の中で、言い訳がましく言った。 待て待て、なんで僕が「私が間違って理解しておりました。申し訳ありません」みたいな態度をとらなくちゃイケないんだ? むしろ、「騙された」と文句を言ってもいいくらいだ。 「あ、それは、屋号みたいなもんです。私の名前が『有田』ですから。だから、最初の一文字を取って、カッコを付けたんですね。紛らわしいでしょ。わざとなんですけど」 なんてこった。 インチキクサイのは「主任」だけじゃなくて、「(有)」もだったのだ。 「でも、仕事の内容も、報酬も、きちんとしてますから安心して下さい」 それについては僕も疑いの気持ちを持ってはいなかった。なんというか、清花の仕事ぶりというか、プロ意識というか、そういうのを目にしているから疑いようもない。仮払いと称して現金まで握らされている。 なるほど「主任」も「(有)」も、信用のためのハッタリだったのだ。 「まあ、とにかく見てよ。結構いい報告書になったわよ」と、清花は社長(会社組織ではないから、正確には社長ではないのだが)に手渡した。 山本ふね氏は写真のコピーでおわかりいただける通り、店を閉めた後も毎日店内の清掃に余念がありませんでした。 この店は私と共にあり、私と共に果てる せめて私が生きている間は、美しいままで。それは店への愛であり、この店とともに生きてきた誇りでもあったのでしょう。 「私が死ねば、掃除をする人もなく、荒れて朽ちていく。自分と共に。けれど、それでいい」 常連客でもあり親しい友人でもあった方によくそうおっしゃっていたようです。 山本ふね氏の半生はこのお好み焼き屋と共にありました。 そして、ともにこの世を去ったのです。 以上が、報告書の2ページ目である。1ページ目は表紙だから、この2ページ目が実質報告書の一枚目ということになる。 そして、以降のページには、いくつかの証言とともに、その結論に至った過程や考証を詳述した。 よく読めば、大繁盛をしていたわけではないけれども、近所の人たちに親しまれ、愛されてきたこの店が、『無くなってしまうのは残念に思っている』というのも読み取れるのだけれど、それ以上に報告書全体のトーンは、『私が一生かけてこのお好み焼き屋を守り抜いたように、息子や孫たちにも、自分の選んだ仕事を最後まできちんとこなして欲しい』という色彩に彩られている。 「うん。良くできています。いいですねえ」と、有田はゆっくりと大きく頷いた。 「ただ、ちょっと気になることがないわけでもないんです」と僕は言った。 「言ってみてください」と、有田。 「これが生者、つまり依頼者のための調査だってことは、わかります。だから、依頼者に配慮した報告にしなくてはいけないっていうのも理解できます。けれど、これだと、『お店がなくなって残念』ていうニュアンスが、弱すぎるように思うんです。たとえ依頼者がお好み焼き屋を継ぐことができないにしても、残念をもう少し強調したってよかったのではないかって思うんですが」 「いや、この程度でいいでしょう。だって、ほら、人の気持ちっていうのは、周囲の色んな人に影響を受けて、変わっていきますよね。だったら、死後に気持ちが変化してもいいんじゃないでしょうか?」 |
|
「良かったね、社長のオッケーが出て」と、清花。 「犯罪まで犯したんだ。オッケーが出て当たり前だよ」と、僕。 「今日は気分がいいし、もう仕事はやめにして、飲みにでも行こうか?」 「賛成」 「よお〜し。じゃあ、今日は特別に清花ちゃんが奢ってあげる」 「いいの?」 「だって、学費稼ぎのバイト君に、お金を出させるわけにはいかないでしょ?」 「あ〜〜!!!」 学費稼ぎ。 バイト。 しまった、すっかり忘れていた。 確かに清花と出会った日は、バイトの無い日だった。 だけど、その後は……。 僕は何らかのローテーションに毎日入っていた。 なのに、「休ませてください」の連絡ひとつ、入れていない。 「どうしたの? 大声出して」 僕はバイトを無断欠勤してしまったことを清花に話した。 「あはは。どんくさ〜い」 「笑い事じゃないよ」 「だって、無断欠勤でしょ? 今更謝ったって、手遅れよ。だったら、笑うしかないじゃない」 「ったく、人事だと思って……もう、間違いなくクビだよ」 「だって、ヒトゴトだもの」 清花はケタケタと笑い続ける。 そうとも。確かに笑うしかない。けど、笑ってたって、明日のバイトはもうないんだぞ。どうやって生活するっていうんだ。 いや、貯金はある。けど、それは学費のためのものであって、生活のために取り崩すことはできない。 「暢気に酒なんか飲んでる場合じゃない。明日からのバイト、探さなくちゃ」 「もう。1分1秒焦ってもしょうがないじゃない。今日はほら、飲みに行こうよ。まだ日も高いし、こんな時間から酒くらってられるなんて、ちゃーんとお仕事を終えた人の特権。明日からのことは、明日、考えよ。ね」 清花が腕を組んでくる。 「ま、確かに、な」 1分1秒、焦ったってしょうがない。その通りだ。 仕事を終えた開放感からか、清花は明るい。僕の知っている清花の中では、特段に明るい。しかもこうして無邪気に笑いながら、腕を絡めて身を寄せてくる清花の、とびっきりかわいいことといったら、ない。 こんな子に誘われて応じなかったら、男じゃない。 据え膳食わぬは武士の恥というじゃないか。 もっとも、武士は食わねど高楊枝ともいうけれど。 いったい、どっちだ? どっちでもいい。「君子危うきに近寄らず」と一緒で、人間は頭がいいから、どんなことにでも理屈をつけて正当化してしまう知恵を持っている。 「主任」も、そう。「(有)」も、そう。気楽に正当化してしまえば、それだけで解決することが世の中にはたくさんある。 「ま、そういうことに、しておこう」 「何を1人で納得してるのよ」 「なんでもない、なんでもない」 僕は清花に連れられて、一軒の居酒屋に入った。 個人経営らしいそのカウンターだけの小さな店はまだ準備中だったが、清花の顔を見ると「いいよいいよ」と言ってくれた。 「ごめんね〜。こんな時間から」 「ほんと、迷惑だよね〜。開店前と閉店後ばかりに来るんだから」 すかさず、おしぼりが出てくる。 それから、注文もしていないのに、生ビールの大ジョッキがふたつ。 「アテはまだ、ロクなの、できないけど」 「なんでもいいって」 清花がジョッキを持ち上げる。僕もジョッキを持ち上げる。 2人でカンパイを唱和すると、袋のままポテトチップスがポンとカウンターの上に差し出された。 確かにロクなアテではない。 「そうそう、和宣、渡すものがあったんだ」 「なに?」 清花はセカンドバックから、プラスチックのケースに入った100枚入りの名刺を取り出した。 「え? 名刺? まだたくさん残ってるよ。ていうか、もう必要ないだろ?」 「ちゃんと、見てよ」 「ちゃんとって……?」 そこには、「(有)オフィス風の予感 調査技術士 橘和宣」と書かれていた。 「なんだよ、これ。調査技術士?」 「だって、同じ肩書きの人がコンビを組んで仕事するなんて変じゃない。普通は先輩と後輩とか上司と部下とか、営業と企画とか、一般社員と専門技師とか、立場が違う人がコンビを組むでしょ?」 「それはいいけど、いつこんなもの用意したの?」 「最初から。二人で行動することもあるかな、とか」 「嘘。山本さんの件が解決したら、清花の案件も手伝わせるつもりだったんじゃないの?」 「まあ、ね。せっかく作った新しい名刺なんだから、無駄にしないでね」 「無駄にするも何も、明日から僕は別のバイトを探さないと……」 「だからあ、こうして失業者に愛の手を差しのべてるんじゃないの。明日からも、手伝ってね」 しれっとして清花は言う。 そして、次の瞬間には、ビールをぐいぐいと喉の奥に流し込んでいた。 愉快そうに笑顔を浮かべながら。 運命は時に、なんの前触れもなく、新たな展開をみせる。 僕の場合それは、ひとりの女性との出会いだった。 彼女は春の太陽だった。 夏の照りつける太陽ではない。あくまで春の太陽だ。 ……と思ったのは大きな勘違いで、清花は夏の照りつける太陽だった。 |
